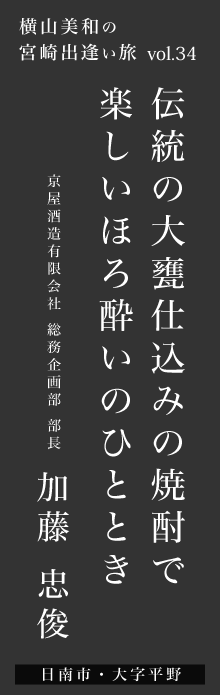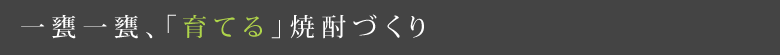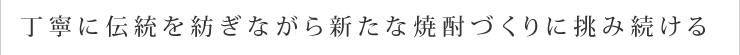今年の宮崎の梅雨は、とにかく雨、雨、雨。日南市にある京屋酒造に取材にうかがった日もやはり雨でした。車をとめてまず目に入ったのは併設する水田で泳ぐ合鴨たち。一列にきれいにならんで土手を歩き、すいっと一羽が田んぼに入ると、約20羽の合鴨たちが一斉に泳ぎ始め、水田の中の草や虫をついばみます。こうして作られた「あいがも米」も、京屋酒造の焼酎の原料の一部として用いられます。
大正初期から使われているボイラーや蔵に立つ煉瓦煙突などジブリの映画の世界に足を踏み入れたような焼酎蔵で、副蔵長で農業生産法人アグリカンパニー代表の加藤忠俊さんにお話を伺いました。
京屋酒造の焼酎づくりは、農業から。伝統的なヨーロッパのワインシャトーのように農業としての焼酎づくりはできないかと考え、子会社農業生産法人アグリカンパニーを立ち上げました。自然と環境に優しい焼酎をつくろうと、農薬を使わず有機肥料を用いた農法で、宮崎の豊かな水と土との対話を20年近く続けてきました。
原料の甘藷は子会社農園以外はすべて国産で、地元宮崎や隣県である鹿児島から買い付けをしています。また、米はアグリカンパニーで栽培する「あいがも米」をはじめ、九州産を中心とした国産のうるち米を使用しています。


京屋酒造は、天保5年(1834年)江戸時代の後期に創業といわれ、伝統の大甕仕込みで焼酎を作り続けています。酒造の全行程で使われる大甕。とはいえ、その容量は800リットルと、現代の焼酎づくりで使われるものとしては小さなものとのことです。土に埋められた甕がずらりと並ぶ様子を実際に見せて頂きましたが、発酵がすすむ独特の香りが蔵に漂い、もろみがぽこっぽこっと沸き立つ様子をみると、焼酎を「つくる」というよりも、命あるものを「育てている」ような不思議な感覚がしました。ちいさく、ぽこっと沸き立つ甕があれば、大きな気泡がはじけ甕の中のもろみが音をたてて動くものあり、その様子に寄り添いながらそれぞれの甕の温度管理などを行って焼酎は大切に「育てられて」いました。
本格焼酎の製造工程は、大まかに言うと米や大麦に麹菌を加えた後に水と酵母を加える一次仕込み、そして、一次仕込みでできた一次もろみに、蒸して粉砕した主原料の甘藷や大麦を加えて発酵させる二次仕込みへと進み、蒸留、熟成させて焼酎へ姿を整えていきます。原料の蒸し上げや、甕壷の洗浄、蒸留まで用いられるのが、蒸気を作り出すボイラーです。京屋酒造では、現在県内ではほとんど姿を消したコルニッシュボイラーを大切に使い続けています。柔らかい熱で水分を多く含んだ蒸気を出し、その温度を保ちやすいとされるコルニッシュボイラーが京屋酒造の製品に独特の味わいをもたらしています。


製造工程の見学の中で一番印象的だったのは、蔵の外に出て眺めた煉瓦造りの煙突です。雨にぬれた赤黒い煉瓦煙突の存在感は独特の存在感を醸し出していました。建築年は不明とのことですが、取り壊しをせずに強化工事を行うことで蔵の象徴的な存在になっています。
降水量が多い日南の豊かな水の恩恵を受けながら、有機農法にこだわる土作りに果敢に取り組むところから始まる焼酎づくり。先人たちから受け継いた施設を大切に使い続ける、丁寧な伝統の紡ぎ方。
こうした想いを受けて、京屋酒造の商品ひとつひとつを眺めてみるとモンドセレクション金賞など多くの受賞歴のある大甕仕込み「甕雫(かめしずく)」や、創業年の頃に起った「大塩平八郎の乱」をモチーフにした「平八郎」など、それぞれに込められたストーリーを感じることができます。
ワインのような佇まいと楽しいネーミングが興味をそそる「河童の誘い水」など多彩なラインナップの京屋酒造の焼酎。気の合う人と焼酎を囲んで、楽しいほろ酔いのひとときを過ごす様子を想像するだけで思わず笑みがこぼれる、そんな今回の出逢い旅でした。